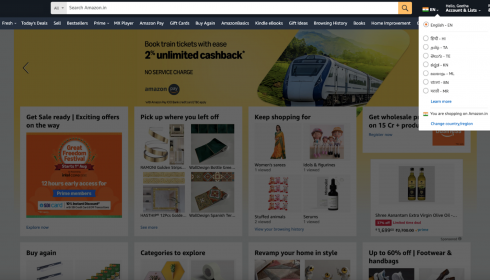UPIとインドのキャッシュレス経済:日本の決済戦略への警鐘
インドは今、都市・地方を問わず消費の地殻変動が進行中。
25年以上、数多くの著名企業の国内・グローバルマーケティングを支援してきたイーライフは、日系パートナー企業様がインド進出の第一歩を確実に踏み出せるよう、現地生活者の視点を丁寧に拾いながら、手探りの第一歩を支援します。
本コラムでは、インドに精通した4名が、それぞれの視点から現地の最新事情や気づきを発信していきます。多様な切り口で、変化の真っただ中にあるインドの“今”をお届けしてまいります。
▶ 執筆者プロフィールを見る
はじめに
こんにちは。Geetha Anandです。
日本はテクノロジー面で目覚ましい進歩を遂げているにもかかわらず、デジタル決済の普及という点では大きく遅れをとっています。スマートフォンが広く普及しているにもかかわらず、日常の小さな買い物では現金が依然として主流です。一方、インドは統一決済インターフェース(Unified Payments Interface. 以降UPI)を中心に、急速にデジタル決済システムを構築し、今や毎月数十億件の取引を処理しています。このギャップは、日本の企業や政策担当者に対して、「いまのままのやり方で本当にいいのか?」という問いを突きつけています。
インドでのUPIの成功は、単なるテクノロジーの話ではありません。誰でも使える仕組みによって金融サービスの利用者を広げ、モバイルを中心にサービスを設計し、消費者との関係をより深く築く——そうしたマーケティングの原則が、インドの成長を支えているのです。これは、日本にとっても戦略を見直すうえで大きなヒントになります。
インドはキャッシュレス経済への適応において世界のリーダーとなっており、UPIは決済のあり方を根本的に変える役割を果たしています。UPIは、モバイルデバイスを用いた銀行口座間の即時送金を可能にします。その迅速な普及により、インドはデジタル技術を通じて誰もが金融サービスを利用できる環境を実現しています。
2025年現在、UPIは毎月160億件以上の取引を処理しており、ピア・トゥ・ピア決済、店舗決済、公共料金の支払いなど、あらゆる用途に使われています。この爆発的な成長は、利用のしやすさ、手数料ゼロ、プラットフォーム間のシームレスな相互運用性によって支えられています。屋台から高級店に至るまで、QRコードとモバイル決済の普及により、銀行口座を持たない人々でさえ、正式な経済活動に参加できるようになりました。
インドの日常に根付く決済手段

モールでの買い物から、公共料金の支払い、路上での野菜購入まで、UPIはすでに何百万人ものインド人にとって当たり前の選択肢です。財布を忘れても、スマホがあれば問題なし。お金が足りなければ、家族や友人にQRコードを送って支払ってもらうこともできます。スムーズで迅速、そして安全——それがUPIの力です。
支払い方法は簡単で、(QRコード読み取りなどや電話に登録された電話番号等の情報から)連絡先を選択し、金額とUPI PINを入力して認証するだけで、すぐに確認メッセージが届き、送金は完了します。
バンガロールの歯科医ディーピカさんは、診療所ではこれまで様々な決済手段を試してきましたが、UPIが登場してからは、ほとんどの患者がこれを選択していると言います。スピーディーで効率的、時間の節約になります。高齢者にも便利で、カードや現金に頼らず、(UPI Liteを使用すれば)パスワードすらも不要です。
例えば、15歳の男の子が治療を受ける時、現金を持ち歩かなくても診療後に母親にQRコードのスクリーンショットを送れば、彼の母親はそのQRコードを読み取ることにより即時に支払を完了することができます。彼女は、「ホステルに住む娘が月末にお金が足りなくなるとメッセージを送ってくれば、どこにいてもすぐに送金が可能だ。」と言います。
いくつかUPIの活用例を挙げましょう。
*バンガロールの主婦プーナム・カピラさん:
「UPIは面倒がなくて使いやすく、素早い取引ができます。一つのアプリで複数の銀行口座を連携でき、切り替えも簡単です。手数料もかかりません。私はもうほとんど現金を持ち歩いていません。」
*バンガロールの果物売りセリバさん:
「以前はお釣りの用意が難しくて、お客さんを逃してしまうこともありました。でもUPIのおかげで、そんな問題はなくなりました。商売がやりやすくなって、お客さんとのつながりも深まりました。小さな商売をしている者にとっては本当にありがたい存在です。」
*チェンナイの金融業のヴェンニラさん:
「母が田舎の病院で新型コロナの入院を必要としたとき、前払いが求められました。現地には現金がなく、私もまだチェンナイから向かっている途中で、どうすればいいか途方に暮れていました。そんな時、UPIで即時送金でき、母はすぐに入院できました。命の恩人のような存在です。」
*タミル・ナドゥの農村出身でバンガロール在住の工学部生ミトゥンさん:
「学生にとってUPIは生活必需品です。学食での軽食、教材の購入、友人との割り勘、すべてがUPIで簡単に済みます。ATMを探す必要もなく、親も即時に送金してくれるので本当に便利です。」
日本の決済システムを知る知人からもこのような声が聞かれました。
*バンガロールのエンジニア、アナンドさん:
「日本を訪れて現金主義に驚きました。買い物のたびにお釣りを慎重に数え合う必要があり、時間がかかります。UPIに慣れている身としては不便で、現金の持ち歩きが面倒でした。」
*大阪在住のAIエンジニア、アビラシュさん:
「日本では現金が主流で、UPIのような便利な仕組みがないと非常に不便です。箱根の観光中に現金がなくなり、1km近く走ってATMを探しました。UPIならこんなことにはなりません。」
UPIの経済効果とは
UPIの拡大は、実際の経済成長にも寄与しています。
『IJFANS.org』の研究[*1]では、カーナタカ州の農村部の小売業で、デジタル決済の導入により月間収益が15%向上したと報告されています。
『IJRPR』[*2]によると、2024年2月時点でインドのデジタル決済総額は約21兆ルピー(約2.52兆ドル)に達し、うちUPIが2024年3月時点で全体の81.8%を占めています。
また、UPIは2017年から2023年の間にGDPの約1.5%を押し上げた[*3]とされ、小規模ビジネスだけでなく、国家経済全体の成長を牽引しました。『JETIR』に掲載されたデリーの事例[*4]では、年間売上が46.7%増加した小規模事業者も確認されています。
デジタルインフラとモバイル主導設計
インドのデジタルインフラはモバイル主導に最適化されており、UPIの成功の鍵となっています。世界銀行によれば、インド人口の60%以上がインターネットを利用しており、GSMA Intelligenceによると、2025年1月時点でモバイル接続は人口の76.6%[*5]に達しています。これにより、アプリ中心のUPIの利用が促進されました。
一方、日本はインターネット普及率が高いものの、まだまだデスクトップ志向が強く、モバイルファーストの流れとは異なるようです。インドのモバイルファーストのデジタル商取引は急成長中で、2029年までに5億人以上のオンラインショッパーが見込まれ[*6]ています。
インド市場進出のための指針
日本では依然として小規模な取引を中心に現金が主流のようです。現金を好む国民性、ATMの充実、現金対応インフラの整備が、デジタル決済普及を妨げており、企業によるマーケティング施策の実行や検証にも負担が大きくなります。
また日本では、複数の決済手段(QRコード、ICカード、銀行アプリ)が併存することからプラットフォーム間の相互運用性が乏しいのに対し、UPIは政府が支援する信頼性の高い統合インフラを提供するシンプルで統一されたモバイルファースト設計です。AmazonやFlipkartなどのインドで主流のオンラインショッピングプラットフォームでも、UPI対応がされているため、テストマーケティングは容易で迅速なPDCA実行が可能となります。
インド市場でのブランド確立は早期の決断と進出が重要であり、柔軟な戦略と現地適応が成功の鍵となるでしょう。
日本企業の誤解とインド市場の可能性
依然として、「インドは現金主義で、デジタル決済は信頼できない」と考える日本企業は多いようですが、近年の発展により小規模商店ですらUPIを受け入れ、地方都市においても普及しています。What’sApp(インドで主流のコミュニケーションツール)やアプリを使った取引が主流で、プレミアム製品の購入にも利用されています。
インド市場への不安(規制の複雑さ、市場の不確実性、決済の安全性)は、現地パートナーの活用、信頼性のあるプラットフォーム利用、UPIなどの簡易で安全な決済手段で緩和可能です。
UPIはリアルタイムで追跡可能な決済を可能にし、現金管理の手間を削減します。「Make in India」や「Digital India」といった、インド政府が主導する経済とデジタル化の発展を目的国家プロジェクトも進んでおり、透明性と法令順守が向上しています。
結論
UPIとデジタル決済の成功は、テクノロジーの力を活用して、国民の所得や居住地に関係なく誰もが簡単に経済活動に参加できる環境を築く上で、極めて実践的なモデルとなっています。こうした動きは、企業にとっても低コストで迅速な市場テストや商品販売が可能になるという、拡張性(スケーラビリティ)と包括性(インクルージョン)の両立を実現しています。
日本企業にとって、インドは単なる進出先ではなく、戦略を再設計し、モバイルファーストの解決策を取り入れ、従来のビジネスモデルに挑戦する場です。
現地文化、消費者行動、法規制の深い理解が成功の鍵であり、現地企業との連携、AmazonやFlipkartの活用、モバイル主導の市場環境への適応が、円滑な参入と長期的な持続性を確保します。柔軟性と協調性をもってインド市場に向き合う企業こそが、この急成長するデジタル社会で成功するでしょう。
[*1]
https://ijfans.org/uploads/paper/12f6cef04c996b91049b199ee5794ff7.pdf
IJFANS(International Journal of Food and Nutritional Sciences)
“The Impact of Digital Payment Systems on Small Retail Businesses in Rural Karnataka”
2024年
[*2]
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap152_e_rh.pdf
Bank for International Settlements(BIS/国際決済銀行)
The organisation of digital payments in India – lessons from the Unified Payments Interface (UPI)
2024年
[*3]
https://ijrti.org/papers/IJRTI2501080.pdf
IJRTI(International Journal for Research Trends and Innovation)
“A Study on Unified Payment Interface (UPI) and its impact on the Indian Economy”
2025年
[*4]
https://www.jetir.org/view?paper=JETIR2208632
JETIR(Journal of Emerging Technologies and Innovative Research)
“Evaluating the Impact of Digital Payment Adoption on Small Businesses: A Case Study Approach”
2022年
[*5]
https://datareportal.com/reports/digital-2025-india
Digital 2025: India — DataReportal – Global Digital Insights
GSMA Intelligence
[*6]
https://www.globenewswire.com/news-release/2024/12/30/3002507/28124/en/Growth-Trends-in-India-s-E-Commerce-Market-2024-2029-500-Million-Online-Shoppers-by-2029-India-Poised-to-Become-One-of-the-World-s-Largest-E-Commerce-Markets.html
Growth Trends in India’s E-Commerce Market, 2024-2029 – 500.
2024年
執筆者プロフィール
越境ECに必要なすべてを、
グローバルオムニチャネルでサポート